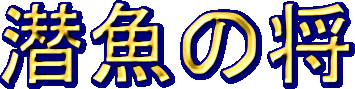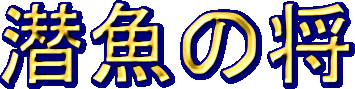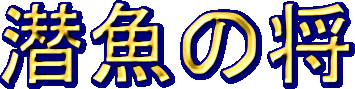
楽文謙という人は魏王曹操に仕え、目立たない地味な人柄ながらも、魏国にその人ありとしてうたわれていた。武勇
に格別すぐれているわけでもなく、知略を讃えられることもない楽文謙であったが、精勤と誠忠をもって魏王に讃えら
れ、一軍を任せられる将として認められていたのである。
だが、万事に控えめで誠実な人柄であったので、長く一線で活躍しながらも、どうしても軍の頂点に立つことはなかっ
た。魏軍には彼以外にも多くの勇将がいた。魏王に認められる勇将の尤もたる人はその時に応じて常に流転し流動し
たが、楽文謙はその座に付いたことは一度もなかった。彼は常に四番か五番の場所にひっそりと佇んでいるのであっ
た。魏軍には盲夏侯として知られる猛将夏侯惇、疾風のごとき武勇を見せる白地将軍夏侯淵、泣く子も黙ると言われ
た張文遠等がいた。そして数々の武名は常に彼らの上にあった。
楽文謙はひっそりと曹操に仕え続けた。魏王に仕えて三十年。彼もいつしか年老い、建安二十三年にはもはや軍務
を退き、この年に家督を息子の楽林に譲った。
楽林という男は父に似ず、激しい気性の若者だった。彼は父の控えめな性格、態度において全てが不満だった。彼
は父の文謙が、張文遠達と比較され、常にその下風に立たされるのを残念に思った。
父の評判はその子の評価、地位にも影響した。夏侯惇の息子の夏侯子休が、たいした才覚もないのに魏王の娘を
与えられたり、張文遠の息子の張虎が故もなく将軍に任じられたのは彼らの父の力が強く働いていたことによる。しか
し楽林はそれまで召し出しはなかった。魏王に目どおりすることもなく、彼は市井で歎を囲った。しかしそんな彼も父の
引退と共に、ようやく一人の将として独立を果たすこととなったのである。
洒落たことの好きな魏王が「二世の宴」を催すことにしたのは楽林が魏王の元に出仕してすぐの出来事であったので
ある。
「小楽殿、今度魏王様が開かれる宴に出られるつもりと聞いたが、本当なのかね」
卓を挟んで楽林と丁度向こう側の老人はやや物憂げな表情を額に浮かべると、眉間に大きな皺を寄らせた。丁度彼
は政策についての講義を終えたばかりであった。
賈文和はもう七十に近い老人であった。若年より策士として活躍した、次々と己れの主を変えたやり口は、世間より
変節漢の見本として悪名を被っていた。魏王に仕えるまでに彼は主人を五度も変えた。彼自身もそんな世間の評判を
知っていたから、魏王より謀士として優遇されながらも人々と深く交わらず、門を閉ざしてもっぱら己れの学問にその精
力を注いだ。しかし老いたといえどもその策の切れはいささかも衰えてはいなかった。
「もう、聞き付けられましたか」
「その位のこと、知らぬわけではない」
「さすがでございますな」
賈文和老人の眼前の青年は口元に少しだけ不適な笑みを浮かべた。やもすれば不遜とも思える態度だった。それだ
けのことを思わせる自信がこの青年からは溢れていたのである。
彼が楽文謙将軍の嫡男楽林であった。父の引退でようやく家督を継いだ彼は、日々自身の将才を高めるために努力
を怠らなかった。いや、それは家督を継ぐ以前からも既に熱心に行なわれていた。かつては魏国随一の知謀を持つと
言われた、しかし決して評判のよくない賈文和老人の元に、兵法を教授されてからもう二年の歳月は過ぎようとしてい
る。
楽林は自身に才覚が必要だと感じた。それは煌びやかな形で人々に示されなくてはならなかった。彼には不思議だっ
た。幾多の将軍達の息子が感心出来る才覚もないのに皆武将の位を受け継ぎ、かつての軍師達の息子が、父に匹敵
する知謀もないのに、今魏王の元に侍っているという事実がである。
しかし彼は今まで武将としての身分がなかった。それは魏王旗下の将軍の子息では唯一のことだった。父の楽文謙
は彼を魏王に推挙しようとはしなかった。おかげで彼は二十代も黄昏近くになるこの日まで、部屋住みを余儀なくされて
いたのである。
「宴に出られてどうなさるつもりだ。やはり、自身の才覚を試されるつもりかね」
文和老人は穏やかに言った。まるで楽林を試しているかのように、その目元は綻んでいた。
「私も楽家の家督を預かる身です。自身の才能を魏王様に識って頂かなくてはなりません」
「では、張虎や夏侯仲権とも争うつもりか」
「私は自分の才能が張虎などに負けるとは微塵も思っておりません」
「ふむ…確かにそれはそうだ」
賈文和老人はうなづいた。楽林は特に張虎には大きな敵愾心を燃やしていた。張虎の父の張文遠は魏国随一の名
が高い武将で、戦の時に幾度も先鋒を務めた知勇兼備の名将であった。しかし父親が名将でも息子がそうとは限らな
い。張虎は父の威光で、まだ家督を譲られないうちに既に将軍の位を授けられていた。それにふさわしい才覚があった
とは思われなかった。こうして世間との付き合いを断ち、交流の薄い賈文和老人から見ても、確かに張虎の武勇は二
流程度である。
「そなたは張虎と戦っても十分に勝てる」
「先生にそう仰られると、私は益々勇気が湧いてきます」
魏王曹操は「二世の宴」を催すに当たって、いくつかの趣向をこらした。それは武官達の息子を槍勝負によって競わ
せるということであった。ようやくにして二世の資格を得た楽林にとって、この舞台は自身の認められていない才能を世
に出す格好の機会であったのである。
「…まあ、おぬしが武勇を競うのはわかる。君もあの名将文謙殿の息子なのだからな。しかし君は郭奉孝や荀文若の
息子達とも争うつもりでないのか?武官の君が彼ら文官と智を争ってどうするというのだ?」
「彼らの智恵はその地位に不相応ということを知らしめようと思いまして。一介の武官の方が、よほど知謀に通じてしる
ということがわかれば、さぞかし不面目なことでしょう」
郭奉孝、荀文若というのは、かつて魏王に賈文和老人と共に仕えた知謀機略の士であった。両人ともその才覚は天
下に轟き、機知は魏国の発展を助けた。その両人とも今は既になく、息子達が父の後を継いで魏王曹操の元に出仕し
ている。
「不面目もなにも…よくそこまで無茶なことを思いついたものだな」
「大丈夫ですよ。私も負けると思っての戦いは挑みませんからね。先生に学んだ智恵を全てぶつけ、奴らの化けの皮を
剥ぐつもりです」
「また言ったものだな」
「先生や、先生の息子さんにはご迷惑をおかけしませんよ」
「迷惑もなにも、儂は既に隠遁の身だ。儂の息子も出仕はしていない。迷惑などどうでもいいことだ」
賈文和は少しだけ悲しそうに微笑んだ。この老人にはもう楽しみはほとんどなかった。既に官職とも無縁な存在となっ
て幾年もの年月が流れている。彼は大尉という大臣として最高の位にまで上り詰めたこともあったが、自身の息子に何
一つ処遇せずにこうして門を閉ざしてひっそりと暮らしている。
枯れはてた老人にとって、楽林という男の若さと煌めくばかりの才知は羨ましくもあり、危険でもあった。
「それでは、健闘して参ります故に」
楽林は両手を組んで一礼すると賈文和老人の元を辞した。書斎に一人残された老人は一瞬だけ天を仰いだ。昔の
若い時の気力が少しだけ胸に蘇ったような心持ちであった。
魏国というのは洛陽長安の二都を中心として、北東は遼東、西は西涼、南は荊州の八州を支配する強大な国であっ
た。これに対抗して南に三州を支配する呉国があり、西に二州を支配する蜀国があった。この三国が鼎立し、互いに
覇を競いあった時代を三国時代と呼ぶ。魏王曹操はその時代を担った英雄であった。彼は多くの人材を集め、彼らを
手足のごとく扱うことによってこの乱世の大陸を治め、今や全土の三分の二までを統治するに至ったのである。
まだ二国は存在するものの、既にその勢いは魏に抗うことは困難と成っていた。力による一時の平和が魏に訪れて
いたのである。
長い戦いの間に曹操の将達も既に年老いていた。彼自身とうに還暦は過ぎ、六十も半ばを越して老年を迎えてい
た。魏国は既に二世達の力を期待する時代となっていたのである。
楽林はその二世たちの中で、非常に遅く登場したのであった。遅れてきた男はもはや一刻の猶予も持つことが許され
なかった。父は既に年老い、楽家の運命は、まだ何も実績のない若者の双肩に重くのしかかっていた。
「二世の宴」と名付けられた催しは建安二十三年の晩春に行なわれた。激しい大陸の寒さも通り過ぎ、穏やかな日々
が訪れ、老骨の魏王の肉体も、やすらぎを取り戻していたのである。魏王は自分に仕えている男達の息子を数多呼び
集めたのである。場所は都の銅雀台と呼ばれる場所であった。
十数年の昔、魏王がこの土地より銅製の雀の彫像を掘り起こしたので、この台にはそのような名前が付けられてい
た。それ以来、この場所は魏王の一番の遊び場となっていた。魏王はこの台で詩を読み、文官達と政治を語り、眼下
で武官たちが己れが武勇を示すのを眺めた。その都度魏王は自身の国の優勢なことを悟り、満足するのであった。
呼び集められた二世達は、かくもこれだけの人物をよくも集めたものだと思われるほどの壮麗さであった。彼らの父
親は皆息子の事を気遣い、華美な服装、煌びやかな衣装に身を包んでいた。父がいないものは母がその役目を代わ
りに務めた。豪華絢爛たる貴族の子弟の集まりであった。ただそんな中で楽林だけは質素な鎧に身を包み、賈文和老
人のお下がりの礼服を一着携えてその場に現われたのであった。
「素晴らしきことかな。この魏国を担う若者が一同に会したのだ」
魏王曹操は銅雀台の手摺りにもたれながら静かに杯を肩向けた。そういう彼自身も若き息子曹植を傍らに従えてい
る。三男ながらもその才覚を曹操が最も愛したこの才人を、彼は熟成した大人の目で柔らかく見守っていた。
やがて武官達の行進が眼下に始まった。曹操がその人物を見込んだ武将は幾多もいた。彼らも曹操と同じように年
老いた。今や時代はその息子の時代を迎えようとしていた。事実、曹操も自身の地位を息子に譲ろうと思い始めてい
る。ただ、平凡で控えめな長男曹丕か、才気煥発だが短慮な三男曹植かの迷いはあったのだが。
「見よ、植。彼らがお前と共にこの魏国を支えていくのだ」
曹操は虚空に杯を突き出した。行進していく騎馬の足音が響いてくる。かつては彼も戦場を駆け巡った時代があっ
た。若者たちの足音に頼もしいものを覚えながら、王は過ぎ去った若さを少しだけ懐かしがった。
「先頭に見えるのが夏侯淵の息子仲権だな。次の少し頼りなさそうな奴が夏侯惇の息子か。子休の奴だな」
夏侯淵、夏侯惇の両氏は、曹操軍の中でも屈指の勇将で、その才覚を深く曹操に愛されていた。特に夏侯惇等は、
戦場で片目を射られ負傷したが、その矢が突きささった自身の眼球を「これは父母より賜りし肉体の一部だ。なぜこれ
をむざむざと捨てられようか」と放言し、一瞬のうちにそれを貪り喰らったという程の武将である。しかしその負傷のた
めにその後は軍務に付くことは少なかった。子休はその息子で、父の働きを背景に曹操の娘と婚姻を結び、王の娘婿
となっているが、この人物はとかく評判がよくなかった。貪財の臆病者で、武将としては明らかに不適格であった。
夏侯淵の息子の仲権は父に兵法、武芸を教わり、若年ながらも勇将としての威名が高かった。父の夏侯淵もまだ健
在で、西方の漢中を守る都督として隣国の蜀と対峙している。おそらく、次代の魏軍の中核となるであろうと言われてい
る。
「あいつは張遼の息子の張虎だな。親父に似て不敵な面構えだ。わっはは、植よ、見てみろ、奴の堂々たる様を。張遼
もよく息子を育てたものだわい」
三番目に入ってきた若者を見たとき、曹操は老病で痩せた肩を震わせて大笑した。この若者は、魏軍随一の将と言
われた張遼文遠の嫡男であったのである。父の文遠もまだ健在で隣国呉との国境で、この敵国の動きを監視する大
任に付いている。その偉大な父の七光もあったであろうが、張虎は既に初陣を果たして、一方の将としての器量を讃え
られていた。人々は「虎の父に犬は生まれぬものだ」と讃えたが、張虎当人は「俺が犬ならば名前に虎など付けぬもの
よ」などとうそぶいていた。
そのような名将の子弟が通り過ぎた後、まだ幾人かの子弟達が後に続いた。見覚えのある顔もあったし、父親の武
功が少ないために、覚えてもらえない顔もあった。そうして全ての子弟が通り過ぎた後で、まるで自身の粗末な装いを
恥じるかのように、ひっそりと楽林は入ってきた。
「む…?」
曹操はその若者が誰だかすぐには思い出せなかった。確かにその顔はどこかで見たことがあった。彼は幾度も首を
捻った。そして彼はようやく一つの事を思い出した。楽林の着ている赤装束の古びた鎧は、かつて自身の部下である楽
進文謙が着ていたものであったということを。
「あれは…楽進の息子なのか?そういえばどことなく父親の面影がある。うむ、まるで父親のように地味な男だな」
曹操が抱いたのはその程度の感想であった。彼ももはや老いていた。青年が抱く壮大な野望や煌めく野心を見透か
すことは出来なくなっていた。楽林は父親とは違った。その若い胸の内には強烈な顕示欲が潜んでいることを老いた魏
王は気付かない。
楽林の整列で全ては揃った。銅雀台の前に並んだ若者の一団は、まさに新しい力を如実に表していた。
「若者達よ、互いに戦え。そして父親より譲り受けた技を見せよ」
曹操は台の上より大声を張り上げた。老いたとはいえ、声はまだ武将に威令を行き届かせるのに十分な貫禄と畏怖
を備えていた。
「しかし魏王様、戦えと言われても、どのようにすればよろしいのですか」
曹操の号令に大半の二世の将は身を震え上がらせた。大陸の英雄の前では大抵の人間は縮みあがった。しかし偏
将軍の張虎は怯えの色を見せなかった。確かに彼は虎と名乗るだけの度胸を身につけていた。
「儂に一騎打ちをみせよ。幾人抜けるか競うのだ。五人抜けば美田、七人抜けば美女、十人抜いたものには美邸を授
けようではないか」
魏王の一声で若者たちは再び活気を取り戻した。試合に勝てば、名誉だけではなく、品物まで手に入れることができ
る。その思いが若者の喚起を呼び起こした。
「植、お前にもあの若者たちの元気が欲しいものだな」「父上、私は知恵で勝負する人間です。武事は私にはむかない
のですよ」
「そのようなことを申しては臆病者と思われるぞ」
曹操は傍らの息子曹植を揶揄するような口振りで言った。この息子は才気はあるが、あまりに文人肌過ぎてたくまし
さがなかった。曹操は自身の後をまかせるものとして息子のことを気に掛けた。この辺り、彼も世間の父親と大して変
わりがない。
「では、まず私がいくことにしよう。異存はないな!」 騒ぎの中で、一際響く大声で怒鳴った若者がいた。彼は夏侯仲
権、夏侯淵の一子であった。
豪胆な武将の彼は馬を広場にへと進めた。矛を構え、彼は戦いの構えを取った。
「まずは仲権か。はて、誰がかかったものか。誰か、仲権と勝負するものはおらんか?」
曹操は子弟達の顔をずらりと眺め回した。残されたものは、二人の若者を除いて、皆うつむいて下を向いてしまって
いた。仲権の武勇は既に知られていた。知勇を兼備した彼の戦いぶりは派手ではないが手堅く、そして強い。これに自
身が対抗しえると思っていた者は僅かに過ぎなかった。一人は張虎、もう一人は楽林である。
「声が上がらぬなら、儂が指名しよう。よし、子休よ、従兄弟のよしみでお前がいくのだ」
「わ…わたくしでございますか?」
「くどい。さっさといけ」
曹操の命令を聞いた夏侯子休はその一言で腰が砕けてその場に座り込んでしまった。彼は勇将夏侯惇の息子で、
外見は煌びやかな鎧に身を包んでいたのだが、中身はどうしようもない鈍物であったのである。
彼はぶるぶる震えながら中央に進んだ。しかし彼の勇気はそこまでであった。力強く矛を回し、彼を睨み据える仲権
の姿を見た途端、彼は持っていた槍を取り落とした。
「ま、まいった…」
思わず周囲から失笑が漏れた。相手の仲権も何が起こったかさっぱり解らない顔をしている。魏王ももはやこの娘婿
には呆れ果て、手を額にやるばかりで目も当たられない。
始めからこのようなことで先が思いやられたのだが、とにかく武官達の御前試合はこうして始まったのである。
試合は大方の予想どおりに進んだ。まずは夏侯仲権が五人を打ち倒して美田を己れが手中にした。彼の戦いぶりは
父を辱めないものだった。綺麗にまとまった彼の矛さばきは、優等生的な香が強かったが、とにかく彼は戦いには勝っ
た。
しかし彼の華もそれまでだった。記念すべき七人目には、到頭張遼の息子張虎が登場してきたのである。噂に違わ
ず張虎は強かった。さすが父親が「泣く子も黙る」といわれた張遼文遠だけはあった。彼の槍の速さといえば、その場
にいる将のだれもが見惚れるほどだった。
十数合ほど仲権と張虎は互いの武器を打合せた。その間明らかに仲権は押されていた。最後に張虎が怒号と共に
槍を振り回すと、強力に弾かれて仲権の矛は地面に音を立てて転がった。仲権に替わり、張虎の七人抜きが達成たの
である。
その後の張虎はほとんど無敵であった。八人目を一合で馬から叩き落とし、九人目はすれ違いざまに鎧をつかんで
引きずりおろした。あと一人で張虎は十人抜きをも行なおうととしていたのである。
十人抜きの最後となっていたのが楽林であった。彼はこの時までずっと群衆の片隅に身を納めていた。最後になっ
て、彼はようやくその存在が皆に気付かれた。
「楽林、お前の出番だ」
魏王は最後にただ一人残った楽林に声をかけた。魏王にとっても楽林は目立たない平凡な二世にしか思えなかっ
た。どうせ張虎に打ち倒されて、華を御前試合に添える。曹操はその程度の存在価値しか楽林に見いだしていなかっ
たのである。
「光栄でございます。父文謙の名前を辱めないように全力を尽くすつもりでございます」
楽林は台上の曹操を仰ぐと、両手を合わせて深々と一礼した。自身は十分なほどにあった。張虎は確かに強い存在
であった。しかし自身の力がそれに劣るとは微塵も彼は思わなかった。
「張虎よ、そなたの父張遼は常に楽進の上を行く存在であった。そなたも楽林の上をいくのか?」
「なんの楽林ふぜい、この矛で吹き飛ばしてくれましょうぞ」
曹操の言葉に張虎は呵呵と笑った。楽林は自身が少しも期待などされていないことを知った。所詮世間の目は希代
の名将の息子に向けられている。自分という人間の無名さ、父の名前の頼りなさが、ここまで厳しいものだとは思わな
かった。
しかしその反対で、彼は心中に異様なほどの闘志が沸き起こってくるのも感じていた。張虎などには負けてはいられ
なかった。楽林は矛を静かに構え直した。
「楽林、容赦はせぬぞ!」
血の気の多い張虎は戦意を剥出しにして、いまにも襲いかからんばかりであった。彼の乗る馬も既に足を踏みならし
て、いつでも突撃の体制を整えている。
(勝負は一瞬で決まるな)
楽林はそう見ぬいた。彼は馬を少しだけ下がらせ、腰を低く引いた。張虎が襲いかかって来るのを待つばかりであっ
た。
「どうした、かかって来ぬか!ならばこちらからいくぞ!」
張虎は手綱の一撃を馬に当てた。彼の乗る栗毛の軍馬は一声嘶くと走りはじめた。二人の距離はたちまち縮まって
いく。そして張虎が構えた槍の射程に楽林は捕らえられた。
「とおっ」
鋭い突きが胸元を抉った。と同時に槍を繰り出した張虎に一瞬だけ隙が出来た。その時を狙って楽林は跳んだ。本
当に彼は宙を舞っていた。馬から飛び降りるようにして張虎の懐に彼は飛び込んだ。
「むっ!」
「槍の長さは時として隙を作る!」
大声で言い放つと、楽林は素早く左手の拳を張虎のみぞおちにたたき込んだ。ぐにゃりと鈍い感触が拳の骨を触っ
た。
「くはぁ」
張虎の口から血混じりの反吐の飛沫が飛んだ。彼の予想どおりに勝負は一瞬でついた。張虎はがくりと首を落として
崩れ落ちた。楽林の鍛えられた拳は僅か一撃で張虎の意識を奪い取ったのである。
馬上に突っ伏している張虎を尻目にして、楽林はゆっくりと馬より降り立った。そして少しも気取ることなく、銅雀台の
前に立ち、静かに曹操向かって一礼をした。
「見事じゃ…楽林…とやら…」
あまりにも鮮やかな出来事故に、曹操は舌をもつれさせながらそれだけ言うのが精一杯であった。
「約束通り、楽林には美邸を取らそう。こちらへと上がってまいれ」
少しの時間の後で曹操は興奮から冷め、いつもの冷静な彼に戻っていた。常に平静を保っている魏王を興奮させる
ほどに、楽林の活躍は素晴らしいものがあったのである。
「申し訳ございませんが、その前に少しだけお時間を頂けませんか?」
「何故じゃ」
「今までの私は武官としての私でございました。褒美を賜るのならば、服を変え、文官としての私で頂きたく存じます」
「ほう、しかしそなたに文官としての才があるとは限るまい」
「それもこれから試してみたく思っているのです。この後は文官の御子息がいらっしゃるのではなかってのですか?」
「わっはっは。楽林は自分が文武両道に通じていると言いたいのだな。よし、許そう。しかし恥をかいても儂はしらぬぞ」
楽林の予想に反した答えに曹操は心を擽られた。普段の彼ならば若者のそのような言葉を戯言の一片で済ませてい
たにちがいない。しかしこの日は違った。考えもしなかった楽林という若者の出現に、彼は久方ぶりに心を時めかせて
いたのである。有為な人材を愛し、召し抱えることで曹操は魏王の位に伸し上がった。この若者もまた、彼が求める人
材の可能性があった。
「さあ、早く着替えてこい。こちらで心行くまで語り明かそうではないか」
楽林は手早く礼服に姿を変えた。戦いで乱れた髪を整えて冠を頭にかぶせた。曹操はこの服もどこかで見たような気
がした。だが今度はすぐに思い出した。今は都の片隅で隠遁生活を送るかつての軍師賈文和が着ていた服であった。
「その服は賈文和のものではないのか?」
「その通りでございます。文和様は私の師匠ゆえ、こうしてこの不肖の弟子に礼服を一着賜ったのです」
「賈文和か…そうか、そなたは賈文和の弟子であったのか。あいつめ、人付き合いが嫌いだとかぬかして隠居しおった
が、まだ弟子など持っておったのだな」
「何度も断られましたが、強引に私が弟子にして頂いたのです。師匠は今日のために礼服をくださいました。今度は私
は文官として才覚を見せる番でございます」
「よし、ならばこちらへと来い」
既に銅雀台の上には二人の文官が礼服に身を包み、それぞれの才覚を試すべく、威儀を正して立っていたのであ
る。そしてその二人の後に隠れるようにして曹操の三男曹植がいた。この息子は父親の文人的な所を多分に受け継い
でいた。時折発するひらめきは天才に近いものがあった。しかし反面で臆病であり、武勇には疎い。
「荀粲でござる」
二人並んだ文官の内の一人が頭を下げた。彼は冠ではなく、道士の被る布の頭巾を頭に付けていた。その礼服もど
ちらかといえば道教的な趣味の強いものだった。彼が屈んだ時に少し薬の匂いがした。楽林はこれがあの変人で有名
な荀粲だなと思った。
荀粲とは曹操に仕え、清廉温雅な人柄で知られた軍師荀文若の息子であった。父親は潔癖な大人物であったが、息
子がそうとは限らない。魏王の一族の娘を妻に迎えてはいるが、遊廓と道家の説に狂い、知恵は人並み以上だが、ど
ちらかというと世間ではあの人は阿呆とのもっぱらの噂であった。
「拙者、郭奕と申します」
もう一人の文官も頭を下げた。彼はまた、病的なまでに威儀を正していた。衣服には少しの乱れもなく、不気味なほど
にきちんとした服装でこの男は控えていた。郭奕の父は荀文若と並び称された奇才の軍師郭奉孝であった。父親の後
を継いだ郭奕は学士として登用され、非常に狭量で人を見下す人柄でありながらも、一応一廉の文官として名を世間
に知られていたのである。この二人の父に賈文和老人を加えたのが、曹操が重用した軍師達であった。しかしその二
人は既になく、今や世間から引きこもった賈文和だけが生き残っている。
「その後にいるのが我が息子の曹植じゃ。こ奴にお前たちの誰が優れているかを判別してもらうとしよう」
「ははっ」
一同は曹植の前で頭を下げた。この文人の息子の才覚を曹操は認めていた。そして裏を返せば、この宴に参加した
若者には、密かに彼という人間も含まれていたのであった。
「僭越ながら、私が父上に替わって三人に聞くこととしようではないか。私が訊ねるのはただ一つ!この魏国はどうすれ
ば他の二国を下せるかということだ」
曹植は強く言った。これには他の三人よりも父の曹操の方が遥かに驚いた。彼はこの三男のことを文弱と見ていた。
しかしその臆病と思っていた息子は、まるで君主が軍師に問うように、そう、かつて曹操が彼らの父親に策を訊ねたよ
うに問いを投げかけたのである。
三人は一様に驚きの表情を浮かべた。そして誰もが一度に口を開こうとした。しかしそれは自然に止められた。曹植
は黙って荀粲を指差した。そして彼は次に郭奕を指した。最後に彼は黙って楽林の肩を叩いた。それが返答を許され
た順番であった。
「では申し上げましょう。我が魏国は既に精強で、他の二国を圧倒しております。このまま放置しても天下は自然に魏の
ものとなるでしょう」
父親の良い性格を受け継がず、ひたすら放蕩と無為自然に撤した男の答えはそれであった。道教の教えのように、
無為を尊ぶ答えであった。天下の帰趨は放置しても魏国に転がるという。それが荀粲の答えであった。
「天下を治める魏国としては、王を標榜する蜀と呉は相容れない存在であります。まず不逞な輩の呉から叩くべきであ
りましょう。魏王様はかつて赤壁において呉に苦汁を呑まされましたが、今度は確固たる意志で呉を叩くべきでござい
ましょう」
それが郭奕の答えであった。楽林は思わず口の端を歪めて笑った。なんという無策だと彼は心のなかで嘲笑した。確
かに彼らは自身の父親の力量には及んでいなかった。
二世とは所詮この程度だと楽林は嘲笑った。そして彼の頭の中では、彼らの答えなどとは遥かに一線を画した答え
が出来つつあった。
二人の軍師の息子の返答の稚拙さは曹植にも理解できていた。楽林と目が合ったとき、この王子は思わず含み笑い
をした。
(君の答えもその程度のものなのかね?)
曹植の笑い顔はそう言っているようだった。彼は大きく息を吸い込むと、よく通る声で滔々と言った。
「では、語らせていただきます。私は蜀こそを第一につぶすべきと考えております。呉、これもいつかは討たなくてはなり
ません。しかし呉を倒すのには水船が必要です。これは一朝一夕で揃うものではございません。それにひきかえ蜀は
道こそ険しいですが、輸送路さえ確保できれば、魏に兵糧の心配はございません。ここは呉と同盟しながら、蜀を倒す
機会を常にうかがうべきでございましょう」
「うむ、私も同じことを考えていた。楽林よ、君の勝ちだ。君こそ次代の魏国を担う人物だ。父上、楽林は真の名将でご
ざいます。彼は間違いなく文武を兼ね備えております」
曹植はまた例の薄気味悪い微笑を顔に浮かべた。今度は曹操がぞっとなる番であった。今や彼は間違いなく年老い
ていた。そしてもう楽林のような若い将軍を使うのは自分ではないのだということを悟り始めていた。
だが反面で頼もしくもあった。楽林なら必ず魏を助けるに違いない。父親の楽文謙も、身一つで挙兵に参加し、今の
曹操を造ってくれたのである。
「素晴らしいぞ、楽林よ。私は君の父親に感謝しよう。君のような男を儂に仕えさせてくれたことにな」
少しだけ寂しげな声で曹操は言った。今、魏王でさえも楽林の才覚の前に屈していた。楽林は今、得意の絶頂にあっ
たのである。
銅雀台の日の翌日。楽林は突然父の楽文謙に呼び付けられた。魏王旗揚げの時より従った勇将も老いて体の具合
を悪くし、近ごろは病床に伏していた。その父が突然楽林を呼び付ける。何事かと彼は思い、そして思い当った。
(きっと俺は誉められるに違いないな)
そのような見通しを彼は抱いた。昨日の彼の活躍で、楽家の名前は魏国に轟いた。楽林は曹操直々にその才覚を
公衆の面前で認められたのである。父上も自分を誉めてくれるだろうと楽林は思った。
しかしそんな楽林を待っていた父の様子は少し違った。老将楽文謙は病床にあったのだが、床をたたみ、かつて彼
が着ていた鎧装束を身につけ、武者姿でこの息子を迎えたのである。
「父上、どうなされたのですか。お体の具合が悪いと聞いていましたが」
「具合はよくない。しかし、お前の行状を聞いて思った。まだお前にはこの家をまかせるわけにはいかんとな。儂はこれ
から魏王に伝えるつもりじゃ。『楽文謙はまだ働けます、息子などよりよほど働いてみせましょう』とな」
「なぜでございますか。私は先日、魏王陛下よりお褒めの言葉を頂きました。曹植殿下からもです。私の将来は約束さ
れているのですよ。どうして父上がそのようなことを」
「お前はあまりにも目立ちすぎる」
一言、ぽつりとだけ楽文謙は言った。吐き出す言葉には苦痛の影が見えた。病は少しも癒えてなどいなかった。長い
戦場働きが彼の体を着実に蝕んでいたのである。「目立つのはいけませんか」
「お前はやりすぎだ。あまりにも自分の才能を顕示している」
「しかし、これも楽家のため…」
「お前が目立つことは余計なことだ。楽家のためにはならんよ」
楽文謙は静かに語った。呼吸は苦しげだが、言葉にはほとんど感情がこめられていなかった。彼は怒ってはいなかっ
たし、悲しんでもいなかった。人の末期はこのようにあるべきとも言えるほどの語り口調であった。
文謙は言う。もっと身を潜め韜晦せよ。自分を大きく見せることは簡単だが、その実力に見合った大きさに自分を閉
じこめておくことは難しい。実際よりも小さく見せるならばなおさらだ。
「お前が自分の才覚を見せ付けなくとも、いずれ、解るものにはわかってもらえる。それよりもお前は自分の才能を見
せ付けたことで、多くの人々の嫉妬をかったのだ」
彼は息子に言った。お前はこれから多くの人々の嫉み、謗りをうけるであろう。それを乗り越えれるほどお前が強い
わけではあるまい。中傷が加われば、楽家の立場も怪しくなる。いつ誰が我々を陥れるか解らないのだ。 楽林は父の
言葉を思いながら、昨日の人々の顔を思い出していた。張虎はまだ忌ま忌ましい顔をしている程度であったが、武官に
見下された荀粲、郭奕の二人など、今にも自分を絞め殺してつかみかからんばかりの形相だったのを記憶している。
そうしなかったのは、単に武官と文官という腕力の差であった故に違いない。
荀家は代々高級官僚を輩出し、政界に及ぼす影響力も強い。荀粲その人は阿呆な殿様としても、その従兄で曹操の
側近荀公達などが口を挟んだら、楽家の立場など危うくなる。
「あの賈文和殿が政界から身を引いたのも、全ては韜晦のためじゃ。いくら才覚が優れていようと、所詮あの人は外
様。荀一族を相手にしたら身が危うい。その考えたあの人が門を閉ざして人付き合いをしなくなってから随分立つ」
ふと楽林の頭に師匠の賈文和の顔が浮かんだ。師匠の力は今政界にあるどの策士よりも優れているように楽林は
思った。「先生はまだ十分中央で通用します」と、ある時楽林は言った。だが師匠は笑って言うだけであった。「こんな老
いぼれにはもはや何も出来ないし、誰も耳をかそうとせんよ」と。そのように仕組んだのは賈文和老人の巧みな韜晦の
術であったのである。
「水草の間に潜む魚のように自身を隠すのだ。迂闊に口を開いてはいかん。そのような軽率な魚は直ぐに釣人に釣り
上げられてしまう。常に潜め。そうすれば釣り上げられることなどない」
それこそが韜晦の真理と父は息子に言った。口を開くことは餌を手に入れることも出来るが、釣り上げられてしまう危
険もある。危険を侵す必要などないと楽文謙は説く。身を隠すことこそ、最も大事で難しいことであった。目の前の餌の
誘惑に勝てる魚は少ない。しかしそれでこそ隠遁の術があるという。まちがって釣り上げられてしまってから後悔して
も、後は行き先は俎板の上でしかない。そうなってから悔いてももはや遅いのだ。
「申し訳ございません、父上」
楽林は全てを理解した。結局自身の行いは、自己満足の範疇から少しも逸脱していなかった。行いはあまりにも余計
なことであった。曹操、曹植の権力者の感心は得られたが、反面で多くの人々の嫉妬をかった。そして父までを不安に
陥れてしまったのだ。
「父上の御言葉肝に命じておきまする。しかし、どうぞ今はゆっくりとお休みくださいませ。そんなに苦しそうではございま
せんか」
楽林は涙を潤ませ、頭を床板に磨り付けて嘆願した。だが、もはや楽文謙にはこたえる力がなかった。彼は体の具
合が悪いときに無理をして起き、しかも甲冑を身につけた。老骨にはあまりにも堪えるやり方であったに違いない。
武装を解き、楽林は父を抱えて再び床に着かせた。持ち上げてみると体はすっかりと羽のように軽くなっていた。思
わず楽林は涙をにじませた。父は最後になるまでやはり控えめな楽進文謙だった。彼は父親の細く衰えた体を抱き締
めた。
その後、いくばくもせずに楽進文謙は死んだ。葬儀はひっそりと行なわれたが、名士たちは次々とその葬儀に詰め掛
け、楽林はいまさらのように父の徳に驚かされたのであった。
それから三十年の時が流れた。楽林は万事に父と同じようにふるまい、ひたすら自分を小さく見せることにつとめた。
謙譲な人柄は多くの人々に愛されて、彼はいつでも憎まれることがなかった。
彼はあの銅雀台での出来事の後は自身の才能を誇ることなど一切なかったが、それでも彼の力を認める者は多か
った。あの二世の宴に参加したもの達が皆死んだり、失態を曝して失脚する中で、彼だけが悠々とその地位を保ち続
けた。
そして彼は今、とうとう荊州の長官にまで伸し上がった。あの宴に加わった若者のなかで彼が最も高い地位についた
のである。しかし彼は慢らなかった。自分の立場を守り、任務を確かに遂行した。人々は彼を父親にちなんで小楽将軍
と呼んだが、そう呼ばれるとき、彼はいつも「私など到底父上に及びません」と言って顔を赤くするのが常であった。
(終)