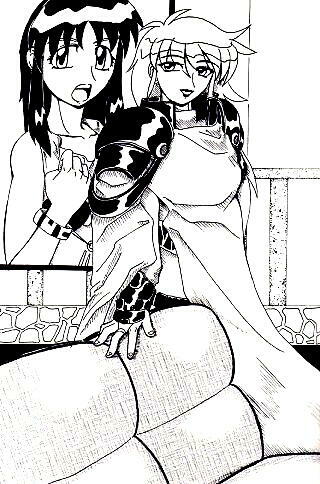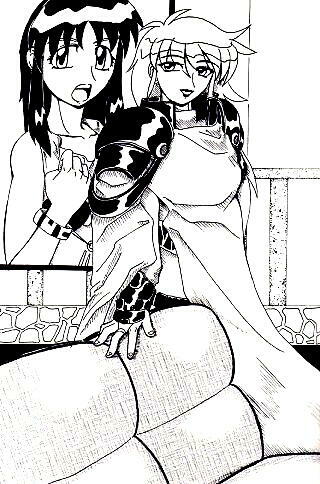第三章 ワンダーガール・メイム
リトルスノーの南。妖精たちの聖域『フレイアの森』に通じる細い道を三人の男女が走っていた。
時刻はすでに夕刻。人陽がゆっくりと地平線の彼方に姿を沈めつつあり、後一時間もしないうちに周囲は闇に覆わ
れてしまうだろう。
「もうちょい急ぐで。このままのぺースやったら間に合わへんかもしれんからな」
「ちょっ‥ちょっと待って…ください」
顔を真っ赤にし息もたえだえになるパメラ。
「あたし…もう…駄目です…」
彼女のこめかみから首筋にかけて大粒の汗があふれ出ては流れていく。パメラは道の真ん中でへたりこんでしまっ
た。
「フォレストさん、少し休みましょう。時間ならまだ大丈夫です」
パメラに水筒を渡しながら、ラニーは懐中時計を見た。時間はちょうど六時を指している。
「焦ってもいい結果は出ませんよ。落ち着きましょう」
「そうやな…」
背中に背負ったライフルタイプの魔銃をそばに置くと、フォレストはゆっくりと腰を下ろした。
「すごい銃ですね」
魔銃を見つめながらラニーがいぶかしげに尋ねる。
「対戦車ライフル型魔銑『オウカ』。わいのとっておきや」
一メートルちょっとはあろうかという魔銃を手に取り、フォレストは自慢げに微笑む。
「あのガキの魔力障壁はめっちゃ強力や。マグナムが効けへん化物でも、こいつの二十ミリ鉄鋼魔弾ならぶち抜ける
はずやさかいな」
肩から下げているガンベルトには、縦長の薬瓶と同じくらいの大きさの弾丸が五発収められていた。重装甲の戦車
を撃ち抜くための弾丸だ。人問に命中しようものなら、一撃で木っ端微塵に粉砕されてしまうだろう。その様子を想像
しラニーは思わず唾を飲んだ。
「はははは…」
頭を掻きながら少し離れた所で汗を拭いているパメラの方に目をやる。だいぶ落ち着いたらしく顔色も多少元に戻
ってきているようだ。
ふと目が合った。何か、言いたげな彼女の視線に慌ててラニーは腰を上げ、パメラの元に駆け寄った。
「パメラ、大丈夫?」
「うん、ありがとう。もう平気よ」
にこやかに微笑んでいるが、だいぶ疲れが溜まっている事は彼女の表情を見ればわかる。
咋夜のあの事件以来まったく睡眠も取らず、食事もほとんど取らずに走ってきたのだ。ラニーですらもう限界に近い所
まで来ているのだ。きゃしゃなパメラなどいつ倒れてもおかしくない所まで行ってしまっている。
「もう少し休んでなよ。出発の時になったら呼ぶからさ」
「うん」
ラニーは立ち上がると、再びフォレストの元まで歩いていった。
「お嬢ちゃんの様子はどうや?」
地図を見ながらフォレストが聞いてきた。
「だいぶ疲れてるみたいです」
「そうか。かなりの強行軍やったさかいな。無理もないわ」
「すみません。足手まといになってしまって」
ラニーは申し訳なさそうに頭を下げた。
「気にすんな。目的は同じなんやし、旅は道連れっちゅうやろうが」
「はあ、道連れですか…」
そういう意味じゃないんじゃないかとラニーは思った。
「でも、そんな古ぼけた本にどれ程の価値があるんですかね?」
フォレストのウェストバッグに入れられている例の本について聞いてみる。
「さあな。でも、あのガキが欲しがっとる事は間違いないんやし、あの赤毛の姉ちゃんの言うことがほんまやとしたら、
大層な本らしいな」
「赤毛の…」
ラニーは図書館で出会った不思議な女性の事を思い浮かべた。
「『ノエル・レポート』って、いったい何やろ?」
フォレストは手に持っていたタバコに火をつけた。
「聞いたことありませんね。パメラは?」
「ぜんぜん」
パメラも頭をふった。
黒ずくめの少女がチェリオをさらっていってしまってから小一時間が過ぎていた。落ち着きを取り戻し、とりあえず自
己紹介を終えた三人は今後の事について話合うことにした。
チェリオを救い出す、ペンダントを取り戻すという事で両者の利害は一致していたので、行動目標はすんなりと決ま
った。そして作戦を決める段階となって出てきたのが、少女が持ってこいと言った物、『ノエル・レポート』についての間
題であった。そもそも、『ノエル・レポート』とはいったい何なのだろうか?三人とも、それについての情報はまったくな
かったのである。
「まいったな。モノが何かわからんようでは、探しようがないで」
「でも、あの子確かこの図書館のどこかにあるって言ってたのよね。図書館にあるんだから、本なんじゃないの?」
左手の人差し指を立てながらパメラがつぶやく。
「そうだよね。レポートって言うくらいだから、紙で出来ているんだろうし...」
「甘いな。水晶玉に記録を残しておくっちゅう方法もあるて聞いたことがあるで。もしかしたら意外なモンがそれやった
りしてな」
「そっか…それに本や記録を残しておく物とは限らないわよ。何か儀式に使う道具だとか…」
「それなら武器や防具なんかも入るよ。小さな道具じゃないかもしれないんだから」
「う〜ん」
三人そろって考え込んでしまう。周囲にある物全てがそれらしく見えてしまい、疑い始めるとキリがなくなるのだ。
「『ノエル・レポー卜』とは、太古の偉大なる錬金術師ノエル・マックフィールドが書き残した研究成果を記した本なので
す。表紙は皮張りの黒い書物で、確か地下二階の四天魔法陣の中央の床にオリハルコンの箱に納めめられ、埋め
られているはずですよ」
聞き慣れぬ声が書蔵内に響き三人はビクリと顔を上げた。
「誰やっ!!」
三人の視線はしばし錯綜し、やがて一斉にある一点を捉えた。書蔵の入り口だ。いつの間に現われたのか、そこに
は一人の見知らぬ女性が立っていた。
「いったい誰や?」
懐のマギウスに手をかけるフォレスト。
「すいません。本を借りに来たのですが受け付けに誰もいらっしゃらなかったので、係の人を捜している内にここまで
来てしまったのです」
両手を上げながら女性は丁寧にあやまる。
燃え上がる炎のような赤い髪を背中の中ほどまで延ばし、羽織った白いマントの下からは黒塗りのプレートアーマー
が覗いていた。物腰や風貌からすれば王宮に仕える騎土のようにも見える。
「立ち聞きするつもりはなかったのですが、偶然聞こえてしまいまして…」
「『ノエル・レポート』について何か知ってらっしゃるんですね?」
ラニーが女性に向かって質間する。
「まあ、おおまかな事は知っていますが…」
女性は先程の内容をさらに詳しく説明した。
「…というわけなんです。わたくしが知っているのはこれくらいです」
「よっしゃ。ほんならさっそく掘ってみることにしよか」
フォレストは立ち上がると、さっさと一人で行ってしまった。
「ちょっと待ってくださいよ、フォレストさん」
ラニーが呼び止めるが、フォレストには聞こえなかったようだ。
「すみません。せっかく教えていただいたのに」
ラニーは申し訳なさそうに頭を下げた。
「いいんですよ。あたしが勝手にお話ししただけですから、気になさらないでください」
女性は座っていたソファから腰を上げた。
「では、あたしはこれで失礼いたします」
マントを翻し、女性は入り口に歩いていく。
「ちょっと待って!」
それまでじっと黙っていたパメラが赤髪の女性を呼び止めた。
「あなた…名前は?」
いつになく真剣な表情をするパメラ。
「メイム・サザーランドといいます」
そう名乗り、女性は帰ってしまった、その後急いで地下一階を調べた所、確かに地下二階が存在し魔法陣が描か
れていた。そして、メイムの言葉通り魔法陣の中央の床から銀色のオリハルコンの箱に納められた一冊の本が掘り
出された。
「何もかもあの女の言うた通りになっとった。感謝せなあかんなあ」
フォレストはタバコの煙をゆっくりと吐き出した。
「そうですね。メイムさんが偶然来てくれなかったら、僕たちあのまま途方に暮れてたかもしれなかったですね」
「まったくや…さてと」
くわえていたタバコをはき捨てると傍に置いておいた同オウカ』を手に取り背巾にかける。
「そろそろ出発しょうか。どうやら目的地まで歩いてあと二時間って所やからな」
立ち上がると爪先をひょいと上げ、靴の裏でタバコをもみ消す。
「デートの基本は男が先に行って待つっちゅうのが常識や。女を待たせたら後が怖いさかいにな」
「ごもっとも。おーい、パメラ。そろそろ行くよ」
木陰で横になっていたパメラに声をかける。しかし、パメラからの返事はなかった。
「パメラ?」
不思議に思ったラニーが覗き込むと、パメラは安らかな寝息をたてて眠っていた。
無理もないか…
ため息を一息つくと、ラニーはパメラを起こさないように慎重に背負い上げた。バッグも首から二人分かけ、剣は邪
魔にならないように腰に巻き付けて動かないようにする。
「なんや。お嬢ちゃん眠ってしもたんか?」
パメラを背負いながら歩いてくるラニーを見て、フォレストはあきれた顔をする。
「すみません。しばらく寝かせてあげてください」
「そりゃかまへんけど…お前がつらなるぞ」
ついこの間まで一般人だったラニーが、傭兵の自分についてきている事だけでもかなりキツイはずなのである
「平気です」
元気そうに言ってはいるが、そうとう疲れている事は顔色を見ればわかる。
「ほんましやあないな。首からかけとる荷物と剣貸せ。わいが持ったる」
「えっ?でも…」
「遠慮すんな。イザっちゅう時に倒れられでもしたらそれこそシャレにならんわい。ええからはよ貸せ」
「すみません…」
二人の荷物と剣を持ってもらい幾分か軽くなった。これならなんとか行けそうである。
「惚れとるな。その嬢ちゃんに」
ラニーのぺースに合わせながら歩いていたフォレストが話し掛けてくる。
「えっ?」
「お前も相当疲れとるやろうに、さっきからそのお嬢ちゃんの心配ばっかりしとるやないか」
「…そう見えますか?」
「他にどない見えるっちゅうんや?」
フォレストは鼻先で軽く笑った。
「子供の頃からずっと一緒でしたからね。パメラがいないなんて事は考えもしたことないです」
「それで、この旅にもつきあっとるちゅうわけか」
「まあ、そんなとこです」
空を見上げるラニー。墨をこぼしたように薄暗くなっていく空に、ポツリポツリと小さな星が光り出し始めていた。
「大事にしたれよ。幼なじみっちゅうやつは、なくしたら二度と返ってこえへんもんやさかいな」
この時ラニーが見たフォレストの顔はやけにさびしそうだった。
「これでよし。傷は少し残るかもしれないけど気になるようなものじゃないよ」
チェリオの肩の治療を終えた少女は、真新しいタオルで両手を拭った。
「わたしの傷の手当てをしてくれるなんて、いったいどういうつもりなの?」
肩に巻かれた包帯を触りながら、チェリオは少女に目を向けた。
襲ってきた時は覆面をしていたのでわからなかったが、少女は緑色の髪をしていた。赤い瞳と緑色の髪。チェリオは
この風体に聞き覚えがあった。
−−−ハウンドリック
暗殺や破壊工作を生業としている部族の一つであった。しかし、この部族は二十年前に法王庁の命により星霊騎
士団に滅ぼされたはずである。
「お姉ちゃんに死なれたりされたら、人質として使えなくなっちゃうからね。あの魔銃使いがレポートを持ってくるまでは
生かしておいてあげるよ」
言いながら少女は、手元に置いた薬瓶からすくい取った膏薬を自分の脇腹に塗った。フォレストに撃たれた傷跡
だ。
「大丈夫なの?」
チェリオが見たかぎりでは、弾は貫通しているようで体内には残っていなさそうだった。だからと言って軽い怪我だと
も言えないが。
「これぐらいの怪我は慣れてるよ。村を襲われた時の怪我はこんなものじゃなかった」
よく見てみれば、少女はまだまだあどけなさの残る年頃であった。体にピッタリとした黒い服と傍らに置かれたショー
トソードを除けば、どこの村にでもいそうな普通の女の子であった。
しかし、それとは明らかに不釣り合いな鋭い眼光が何かチェリオの心に引っかかった。
チェリオはおもむろに置いてあった包帯を手に取ると、少女の腹に巻き始めた。
「何をするんだ!」
「じっとしていて。きれいに巻けなくなるわ」
「よけいな事をするな。これくらいボク一人で出来る!」
「じっとしていなさいって言ったでしょう」
ムスッとしたまま、少女は黙りこくってしまった。
「あなた…なぜこんな事をしている?」
チェリオの質問に、少女の狼のような耳がピクリと動く。
「強盗なんて、あなたみたいな小さな女の子がするような仕事じゃないわ。どこかで静かに暮らそうとは思わなかった
の?」
その、言葉に、少女は嘲るような笑みを浮かべる。
「いかにも平和ボケした一般庶民が吐く言葉だね」
振り向いた少女の目には、絶望や悲しみ、怒りといった負の感情が入り乱れていた。
「友達や仲間を目の前で殺された者の気持ちがわかる?地獄みたいな戦場に一人で放り出されたボクの気持ちがお
姉ちゃんにわかるもんか。人間はいつもそうだ。自分たちの事しか考えない。自分たちさえよければ、他の生物なん
てどうなってもいいと思っているんだ!」
「そんな…」
そんな事はないと言おうとして、チェリオは口をつぐんでしまった。どんないいわけをしようと、この少女の部族を滅ぼ
してしまったのは自分と同じ種族の人間なのだ。王立魔術仕官学校に通っていた頃、ゼルテニア大陸の歴史につい
てもくわしく学んだ。しかし、そのほとんどは人間が主体となって作られた歴史であった。長い歴史の中で人間以外の
たくさんの部族が減ぼされてきた。人間に害を為す、人間に戦いを挑んできたなど理由はいくらでもあった。歴史書に
は全て人間側の、勝者の意見が取り人れられて記されている。人間が正しく、人間意外の部族が悪であったかのよう
に。だが、彼らは本当に悪だったのか?彼らは仕きるために戦いを挑んできたのではないのか?彼らを悪と言うのな
ら、本当の悪は人間ではないのか?
ハウンドリック族が減ぼされた理由も、ほおっておけば人間に害を与えるという理曲からだった。しかし、彼らは生き
るために暗殺の仕事をやってきただけである。そのような仕事を彼らに依頼していたのは、ほとんどが人間だったは
ずだ。そんな身勝手な人間の綺麗事が、この少女に通じるはずがない。この少女も生きるためにこんな事をやってい
るのかもしれない。
「反論なんてできやしないだろ。でも勘違いするなよ。ボクは別に人間に復讐しようなんて思ってもいないし生きるため
にこの仕事やってるんじゃないからね」
ショートソードを手にとりスラリと抜き放つ。黒く塗られた刀身が不気味な光を放った。
「なら、いったい何のために?」
「他にすることがなかったからだよ」
少女は楽しむようにニヤリと笑った。その舌が黒塗りの刀身をぬらりと舐め上げる。
チェリオは言葉がなかった。今の自分にはこの少女には何もしてやれない。なぐさめる事も止める事も…
だが『ノエル・レポート』だけは渡すわけにはいかない。一級魔術師の中でも、ソーサレスの位に就いた者だけに伝
えられるゼルテニア大陸六大秘文の概要。その一つである『ノエル・レポート』は人工生命体の創造と合成についての
高度な技術と秘術が記されているらしい。そのレベルの高さは現代の生物学はおろか、軍事バランスまで変えてしま
うくらいのものだという。そんな物が悪用されでもしたら、それこそ大陸が再び戦火の渦の中へと飲み込まれてしまう。
幸いチェリオ自身も、『ノエル・レポート』が館内にある事は聞かされてはいたが、実際にどこにあるのかは知らなか
った。少女がレポートの事を口にした時は驚いたが、どうやら彼女も館内のどこにあるのかまでは知らなかったらし
い。フォレストや後から来た二人組は言わずもがなである。
「残念だったわね。あなたがお望みのものは絶対に手に入らないわよ。あたしもレポートの在処なんて知らないし、フ
ォレストさんだって知っているはずがないわ」
その言葉を少女は鼻で笑った。
「かまいやしないさ。その時はお姉ちゃんを使って法王庁にでも脅迫をかけるから。さぞかしびっくりするだろうね。自
慢のリムサリア・ソーサレスが人質に取られた上に、秘文の事を知っている者が他にもいるんだからね」
夜の闇よりもなお暗いと思わせるような洞窟内に、憎悪と歓喜の入り交じった少女の笑い声だけがいつまでもこだ
ましていた。
その洞窟の岩陰に炎のような赤い髪の女性が静かに少女とチェリオのやりとりを監視していた。
『知識の箱庭』でパメラたちに『ノエル・レポート』の所在を教えたメイム・サザーランドである。
−−−おもしろくなってきましたね。
メイムはそっと岩陰を離れると洞窟の入り口までやってきた。時刻はすでに十時を廻っており、宝石をばら撒いたよ
うな星が頭上の暗闇を美しく彩っていた。
「舞台は整いましたわ。いらっしゃい。ラニー君」
三人がやって来るであろう地平線を見つめ、メイムはほくそ笑んだ。
「試させてもらいますよ。あなたの力を」